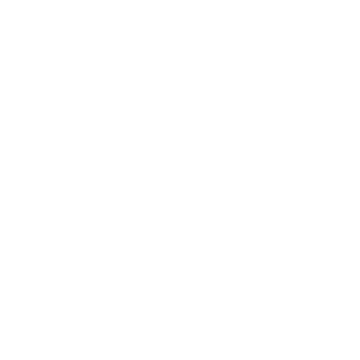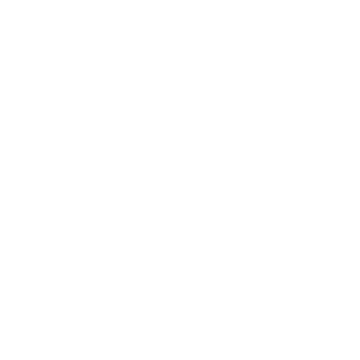猿王悟空ヒーロースキン

武林の者に、神話の英雄、「猿王」孫悟空の物語を知らぬものなどいない。はるか昔、孫悟空は天界で不老不死の魔法の果実、蟠桃の守護者として仕えていた。主人への反抗心を抑えられず、悟空はその桃を食べて不老不死となった。だが、話はここで終わりではない。猿王は、この天界の力は天上の者たちが独占するべきものではないと考えたのだ。だからこそ、悟空は不老不死の桃を携え、天界を抜け出したのである。
かつて故郷と呼んでいた森へと下った悟空は、仲間の猿たちに桃を届けた。しかし、彼らが桃を口にする前に、天界の番人たちが猿王を追って押し寄せた。奮闘空しく悟空はやがて敗れ、山の地下洞窟に閉じ込められた。幾百年経たのち、ある僧侶が孫悟空を解放し、そして大いなる使命を与えた。ヒースムーアへ行き、邪悪な白骨夫人に立ち向かえと。この怪物によって、哀れな戦士たちは恐怖の戯曲の演者として囚われてしまっていた。その恐怖支配に終止符を打つことができるのは、孫悟空だけなのだ。
猿王の物語

パート1
空は晴れていた。太陽は青々とした森を明るく照らし、時折雲が東の風景にぽつぽつと影を落とし、葉を茂らせた太い枝が風に揺れ、遠くの川のせせらぎのような柔らかな旋律を奏でる。虫たちはブンブンと鳴き、動物たちは歌い、または鳴き、それぞれが迫りくる夕暮れに備えようと精一杯動いていた。雲を突き破る火の玉に、気づくものはいなかった。橙色の炎の塊は、目にも止まらぬ速さで空を疾走し、その細くたなびく黒煙の軌跡は、天から続いているかのように見えた。
衝撃が走り、森の歌声が止んだ。落下地点の石や土がはじけ飛び、木の幹が割れて燃えた。しかし、この火の玉の中心にあるものは、何かは分からぬが、止まらなかった。炎が消えると、その塊は人間であることがわかった。いや、むしろ猿と呼ぶが正しい。それは池に投げられた小石のように、何度も何度も地面を跳ね続けた。地を打つたびに猿は鋭い——そしてどこか滑稽な——苦痛の叫び声を上げ、ついにその動きは止まった。
つかの間の静寂は、猿のけたたましい叫びで破られた。「イテテ!」彼は首をさすりながらコキリと鳴らし、その痛みにうずくまり、それから指の本数を数えて、鋭い歯がまだ一本も欠けていないことを確かめた。
「尊き王よ!」と息せき切った声で呼びかけられそれに次々と別の声が続いた。
「お怪我をされたのですか」
「無事にございますか」
「生きておられるのか?」
「きっと怪我をされておられる!」
「腹が減った」
猿王は地面に寝ころんだまま、空を見上げた。次の瞬間、彼の視界に十数もの猿の顔が現れた。どの顔にも、彼の安否を気遣う不安の色が見て取れた。それもそのはず、彼こそが猿の長、孫悟空なのだから。
悟空の目が開いた。「桃はどこだ!」
悟空は如意棒をついて立ち上がる。まるで風になったかのような速さで孫悟空は自分が落ち転げてきた道をたどり、衝撃を受けた場所をくまなく調べ、「桃よ!」あるいは「ないぞ!」と叫んだり、ただ愕然とした叫び声をあげたりした。彼は重い鎧を身に着けていたが、それが彼の動きを鈍らせたり、妨げになるような様子はまったくなかった。猿たちは後を追うのに必死で、しまいには置いて行かれぬよう木々を飛び伝って進んだ。
やがて悟空は、一番大きな穴ぼこの前で立ち止まった。穴の中心まで軽やかに下ると、そこには大きな鞄があった。鞄の口は開いていた。落ちてきたときに開いてしまったのだろう。辺りには桃が散乱し、落ちた衝撃で潰れたものや、燃えてしまったものもあった。鞄の中に手を突っ込むと、まだ数個残っていた。悟空は胸をなでおろした。
「この桃は、天界に住むものたちが独占すべきではない」彼は猿たちに語った。「お前たちにも食わせてやろうと思ってな。これを食えば不老不死になれる。俺がそうなったようにな!さあ急げ、早く食わないと——」
猿王の言葉は、地面を踏み鳴らす不快な金属音によって遮られた。彼らは悟空と同じように空からやって来たが、その着地は彼ほど騒々しいものではなかった。相当な数の天地、将軍、女侠たちが、整然と詰めかける。彼らは得物を抜き、悟空を取り囲んだ。

パート2
「桃を返すのだ!」彼らの怒号が飛んだ。
「おっと、そいつは無理だな」悟空が嗤う。「桃の守り手は俺だ。だったら、俺がその使い道を決めるのが筋ってもんだろ?」悟空は地面にどっしりと立った。そして、笑みを崩さず決意に満ちた
顔で、彼は囁いた。「やれ」
命令を受けた猿たちは、猛々しい声を上げながら木から下りてきた。猿は敵に飛びかかり、殴り、噛みつき、引っかいた。
孫悟空も戦いへと飛び込んだ。高く跳び上がると、宙返りで敵から敵へと飛び移りながら、如意棒で次々と敵を叩き伏せていく。地面に体を投げたかと思えば飛び起き、恐るべき精度で打撃や蹴りを繰り出す。天界の守護者が相手なら、慈悲は無用だった。増長し自らを特別だと驕る者ども、神々の道具、あるいは、ふさわしいと判断した者にしか目を向けぬ組織の執行者。目を向けられぬ者——悟空や猿たちのような者——は無に等しく、路傍の土くれと同じとみなされていたのだ。
兵たちが太い棒や重い岩を振るって戦うなか、悟空は目にもとまらぬ速さで動き、将軍を倒したかと思えば、次は女侠の兜の上で息を整え、そして斬虎に戦いを挑んだ。だがどれほど倒しても、敵は次々と増援を送り込んできた。いかに自分が強くとも、猿を守りながら敵と戦い続けることはできないと孫悟空は悟り始めた。仲間を犠牲にするには、彼はあまりに情け深かったのだ。だからこそ、彼はこれまでで初めての命令を出した。
「逃げろ!」悟空は吠えた。「逃げて身を隠すんだ!」
猿たちは抗議したが、猿王は耳を貸さなかった。
「逃げるんだ!」彼は繰り返した。「奴らは俺に任せろ。俺は戻ってくる、必ずな!」
夜が明ける頃、戦いは森の端、巨大な山のふもとに移っていた。悟空は今、天界の軍勢を相手にたった一人で立ち向かっている。森は暗く、明かりと呼べるものは、ほのかな銀色の月光と、斬虎の攻撃で放たれる紫炎の閃光だけだった。猿たちが遠くの安全な場所まで離れた今、悟空はただ自分の身だけを気にすれば良かった。戦いの合間、食事の時間を作ることができた。悟空といえども戦いは疲れるものであり、精をつけておかなければならなかった(幸運なことに、いくばくかの食料を携帯していた)。
厳しい戦いであったが、彼は楽しんでいた。悟空は繰り出す技の全てに、天界そのものを倒すという意志を込めた。彼は戦いの終わりを待ち望んでいた。そうすれば、桃の入った鞄を携えて、猿たちのもとに戻ることができる。彼らは永遠の命を得て、天界に挑むだろう。
思い通りにならぬことに天界が怒っていると思うと、悟空は嬉しくてたまらなかった。戦いの只中で彼は大笑いした。当然ながら、それは戦っている相手の多くにとって不愉快なものだった。奴はたった一人で戦い、勝ちの目が出てきたと思い… 笑っているのか?またしても、天の力に唾が吐かれたのだ。

パート3
ようやく太陽が新しい日の訪れを告げたとき、悟空は天界からの援軍がもはや来ないことに気づいた。残っているのは、今や癒す味方を失った癒し手の女侠だだ一人だった。
「お前に桃は渡さない」彼女は猿王に言った。
「お前らだけに桃は独り占めさせねえ」彼は答えた。女侠に向かって言ったのではない。それは、神々に向けた言葉だった。
二人の戦士は紫色の炎に燃える木々を背に、互いに向かって突進した。悟空は女侠を跳び越え、背後から頭目掛けて強烈な如意棒の一撃を振るった。倒れた癒し手は、もう起き上がらなかった。
戦いが決着し、悟空は四肢を投げ出した。呼吸は荒く、全身に疲れが溜まっている。ついに成し遂げた。勝ったのだ。天界の軍勢を打ち破り、これで仲間のもとに戻って不死の桃を分かち合うことができる。額の汗を拭いながら、如意棒を杖代わりに体を起こす。
雲一つない夜空を、翡翠色の稲妻が轟音とともに切り裂いた。緑に燃え盛る炎の玉が恐るべき勢いで古き山へと落ち、粉々に岩を砕いた。
全速力で駆けたが、孫悟空は逃げきれなかった。山の巨大な瓦礫が彼の上に落下し、足元の大地が崩れ落ちた。その腕力をもってしても瓦礫からは抜け出せず、ついに悟空は身を任せ、意識を失った。その耳に、歪んだ甲高い笑い声が届いた。それは彼をあざ笑っていた。
「哀れでか弱き悟空め」その声には、嘲りが込められていた。
その声は消え、悟空は暗闇の中にひとり取り残された。彼は桃のこと、そして桃がもたらした破滅のことを思い出した。ただ天界の賜物を仲間と分け合いたい一心だったというのに。今や果たされぬ約束とともに、二度と仲間と会えぬ身となってしまった。彼はここに囚われたまま、永遠に生き続ける。永遠の過ちだ。
桃は賜物などではなかった。悟空は確かに不老不死とはいえ、もはや自由ではなかった。囚われたまま、永遠に生き続ける宿命なのだ。なんと残酷な苦しめであろうか。
あれがもたらしたのは痛みだけだった。
***
瓦礫の下に閉じ込められたまま幾百年が過ぎたころ、悟空はついに誰かが近づいてくるのを見た。それは年老いた僧侶だった。柔和な様子で、敵意は無いように思えた。彼は助けが必要かと悟空に尋ねた。猿王はただ「いらん」と答えた。彼にあるのは、罪の意識だけだった。これは自分への正当な罰だと考えていたのだ。
その答えを聞いた僧侶は、何日も彼のそばに座っていた。二人は言葉を交わした。人生、慎ましい心、物事の因果について。そして、世界にはびこる悪について。それが何週間と続いたころ、僧侶は悟空のもとを訪れ、大いなる使命のことを打ち明けた。
孫悟空はこの使命の重大さを理解していたし、新しい友人が得られる限りの助けを必要としていることも知っていた。そしてついに、孫悟空は自由の身になることを望んだ。自分のためでなく、助けを求める誰かのために。
「行き先は?」埃を払いながら、悟空は聞いた。
「西へ」僧侶は答えた。「ヒースムーアへ」
おすすめコンテンツ

バトルパス
In the arena, enemies of the Khatuns are forced to battle one another to survive. But in the circular walls of this new battleground, warriors have also found that if they fight hard enough, if enough champion blood is spilled by their blade, then something else finds them: the crowd’s admiration. As fame comes to them, prisoners ascend. They become something more. So long as they win.
Battle it out in the Y9S1 Battle Pass. You will have access to 100 tiers of rewards for all 36 heroes.

新しいカトゥーンキャラクター
ハトゥンは、2本の剣を操る残忍かつ機敏な暗殺者集団だ。彼らはグルジンの率いるモンゴルの大軍勢と共にヒースムーアへ侵攻する。その目的は、グルジンが思い描く理想である、長きにわたり民たちを蝕んできた些末な戦乱から解放された平和なヒースムーアの実現。たとえ如何なる代償を払おうとも、グルジンの帝国の元に統一された平和なヒースムーアを作り上げるのだ。