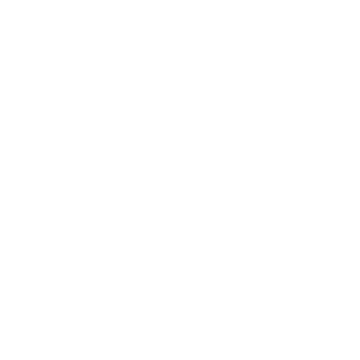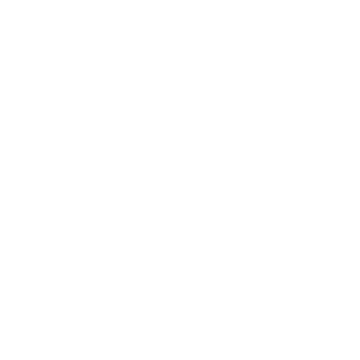達人カタシ 大蛇ヒーロースキン

達人カタシという大蛇について分かっていることは少ない。御沼に住む多くの者にとって、彼は伝承に謳われる架空の存在だ。しかし、それを伝承に過ぎないと思う者ほど、獣道を歩くとき、あるいは村を通り過ぎようとするとき、必ず彼と出会うという。一つ所にとどまらぬ流浪の剣豪カタシは、荒野で横笛を吹き過ごしているとされる。その笛の音を聴いたことのある数少ない者たちは、その音色には悲しみ、深い憂鬱がこもっており、彼が背負う謎をさらに深めているのだと断言する。
剣豪カタシの行く先には常に助けを求める人々がいる。往々にして、それは暴力と抑圧に苦しむ村人たちである。武士道の具現者である彼は、虐げられた者たちのためだけにその力を振るい戦う比類なき達人である。しかし、伝説のムラマサブレードをその手に握ったとき、剣豪カタシは流浪の旅に別れを告げると決める。御沼の人々が安心して暮らすため、そして、耐え忍ぶことを自分の道としたならば、今以上のことをしなければならない。彼の使命は、セイオン橋の前に立ち、侵略者たちを食い止めることだ——たとえ、どんな勢力が相手であっても。
達人

パート1
今夜は、記念の日となるはずだった。平和を祝う日だ。九里の村を故郷とする数十の人々が夕暮れ時に集い、かつての日々を振り返り、先祖の遺産を守り続ける機会に恵まれたことを記念するのである。
しかし、そこに音楽はなく、静けさも、歓声もなかった。その夜こそ、大親分こと文蔵とその手下が、全てを奪った夜だったのだ。彼らには、伝統や文化などどうでもよかった。ただ支配することだけを考えていた。人々はその襲撃の魔の手から逃れようと、村中を逃げ惑った。あらゆる剣や刃物で武装した手下たちは、右から左へと村人たちの命を奪っていった。大通りには死体が散乱し、両脇に並ぶ小さな木造の家は燃えていた。村の広場には、御沼に初めて住みついた人々の一人であったと言われる女性、はるか昔の初代村長の像があった。襲撃者たちに捕らえられた村人たちは、その足元に集められた。
人々はひざまづき、恐怖のあまり涙を流し震えていた。炎に照らされた彼らの前に、文蔵の巨大な影が威嚇するように立っていた。狂ったように笑いながら、彼は次の犠牲者を品定めしながら、刀を無造作に振り回した。それこそが伝説のムラマサブレード、知らぬ者のない刀である。その銘はもはや一振りしか残っておらず、持ち手に一騎当千の力をもたらすという。そして同時に、どんな持ち手も血への渇きに狂わせるとも。村人たちもその逸話を耳にしたことがあった。そして、それが真実だと知ったのである。
文蔵は老いた男の前で立ち止まり、刀をゆっくりと首に押し当てた。しわの多い肌に血がしたたり落ちると、文蔵の笑みはさらに深くなった。
恐怖と反抗心が入り混じった叫び声とともに、やせ細った10代の少年が男を守ろうと駆け寄った。
「父上に手を出すな!」涙と泥にまみれた顔で少年は叫んだ。
文蔵はさらに愉快そうに笑い、手下たちもそれに続いた。まるで巨人が羽根を投げ捨てるように、文蔵は少年を脇に投げ飛ばした。そして血の渇きを癒すべく、刀を掲げた。
だが、それはひとつの笛の音によって遮られた。文蔵の顔から笑みが消え、刀を頭上に掲げたまま辺りを見回した。大通りの奥、村の際を越えた先に、それが見えた。闇に包まれた鎧をまとった男が、文蔵と手下たちに向かって歩んでくる。戦士は急ぐことなく進みながら、まるで目の前の狂気に逆らうかのように、柔らかな笛の音を奏でた。全員がその姿を目にしたとき、柔らかな夏の風が彼の髪と襟巻を横になびかせた。男は大蛇だった。そして、文蔵は知る由もないが、その名をカタシと呼んだ。

パート2
文蔵とその一味から10メートルほど離れたところで、大蛇は立ち止まった。彼はただそこに立っていた。これから起こる騒乱を前に、逃げる気など微塵もない。まるで嵐の中にそびえる巨岩のように。
「迷子か、小鼠!?」文蔵が吐き捨てるように言った。それにつられて、一味の男たちがクックッと笑う。
「いや」カタシは静かに答えた。横笛をしまい、剣を抜く。蛍の羽音のように、鋭い鋼の音が空を切った。カタシが奏でる曲の、最後の一音である。「ただの通りすがりだ」顔を伏せたまま、そう続ける。「いつもな」彼の囁きには、どこか悔しさが滲んでいた。彼は流浪人、根無し草だった。
束の間、静寂が訪れた。風はなく、燃え盛る家々は、遠慮がちにパチパチと音を立てていた村人たちは息を呑んだ。文蔵の仲間たちは武器をきつく握り、戦いの構えを取った。
「やっちまえ!」文蔵が命じた。
手下たちがカタシに殺到し、四方から襲い掛かった。その戦いは、大蛇に捧げる舞のようだった。彼は攻撃を左に右に受け流し、敵を切り伏せ、貫いた。その一連の動作が終わるたびに、地面の死体が増えた。喉が切り裂かれ、首が切り落とされ、ついにカタシの動きが止まり、揺らぐことのない刃が炎に照らされた。ほんの数瞬のうちに、全てが片付いた。手下は死んだ。残されたのは、親玉の文蔵だけだった。
文蔵は呆然と見つめていたが、大きく息をついた。その全身は怒りで膨らんだり、縮んだりしている。「この村は俺のものだ!」そう叫ぶとカタシに突進し、得物で切りかかった。刃が触れようかというその瞬間、カタシは平然と身をひねり、文蔵の体ごと一撃をかわした。そして、跳びあがりながら空中で向きを変え、刀を敵に振り下ろした。深手であったが、それは文蔵の怒りをさらに高めるばかりだった。それどころか、痛みに止まることもなかった。手に持っている刀は天下一の業物だと文蔵は信じていた、それは血を吸う刀だとも。文蔵は破れかぶれで刀を振り回したが、その大蛇はどんな攻撃もかわし、防いでいく。だが、文蔵はついに隙を見つけ、その巨体を使ってカタシを押し倒した。
「俺は一騎当千の男だ!」文蔵が笑った。
カタシは土に倒れ込み、その衝撃の凄まじい重さに驚いた。地面の上で、彼は珍しく笑みを浮かべた。その巨体の親玉は幸運だった。少しは歯ごたえのある男だったというわけだ。あるいは、刀がそうだっのかもしれない。
頭を振って集中を取り戻し、カタシは両手両足で立ち上がろうとした。そのとき、彼と文蔵の間に、羽根のように軽やかな少年が立っていることに気付いた。
「手を出すな」少年はそう言った。かつてそうして父を守ったときのように。その声には、反抗の意志がさらにこもっていた。希望に燃えている声だ。
だが、それは文蔵の不興を買った。今度は、脇に投げ飛ばすだけで済むわけがない。文蔵は少年へと重い一歩を踏み出し、得物を振り上げ、ハエのように叩き落とそうとした。

パート3
カタシにほとんど猶予はなかった。文蔵が動き出す前に彼は起き上がり、少年を救い出した。その一瞬で、カタシは攻撃を防ぎ、文蔵の肩に一撃を加えたのである。
刀を落としたものの、文蔵はまだ立っていた。血を飛び散らせながら、敵めがけて殴りかかるが、それは打ち返されてしまう。ならばと蹴りを見舞おうとするが、カタシも蹴りを繰り出し、その動きを止めた。ついに文蔵は膝を突いた。勝敗は決し、カタシは最後の一太刀を振るった。
カタシが向き直ると、年老いた男が息子を抱きしめていた。
「助けてくださってありがとうございます」男は言った。「息子も、私たちも」
「こちらこそ、その子に礼を言わねばな」カタシはそう答え、少年にほほ笑んだ。
刀を鞘に納め、大蛇は目の前に広がる無残な光景を受け止める。燃える村と、多数の死体。生き残り、苦しむ者たち。彼は、文蔵とその手下たちによって汚された初代村長の像を見上げた。年月を感じさせるシワを顔にたたえた女性だ。彼女はただ、同胞を助け、守りたかっただけなのだ。
少年の父親から、村を救ったことを感謝された。だが、それは救いと呼べるものだったのか、カタシには分からなかった。まだ救われてなどいない。あの人々はただ自分なりの生き方をしたいと願っただけだというのに、全て奪われたのだ。
「またやり直します」カタシの想いを察した父親が、そう言った。「立ち止まってはいられません。それが私たちの生き方です」
カタシは、その決心にただ感服した。雷に打たれたようだった。それこそが、侍の生き方だった。彼らは耐え忍んでいるのだ。
しばらくすると、カタシは少年の前にひざまずき、刀を手渡した。
「お前にやる。これで皆を守るといい」彼はそう告げた。
その後、カタシはムラマサブレードを我がものとし、村の入口へと歩み始めた。
「どこへ行かれるのですか?」父親が尋ねた。
カタシは振り向かなかった。彼は、新たな使命を得た。それは彼の責任だった。
「助けが呼ぶ方へ」
おすすめコンテンツ

バトルパス
In the arena, enemies of the Khatuns are forced to battle one another to survive. But in the circular walls of this new battleground, warriors have also found that if they fight hard enough, if enough champion blood is spilled by their blade, then something else finds them: the crowd’s admiration. As fame comes to them, prisoners ascend. They become something more. So long as they win.
Battle it out in the Y9S1 Battle Pass. You will have access to 100 tiers of rewards for all 36 heroes.

新しいカトゥーンキャラクター
ハトゥンは、2本の剣を操る残忍かつ機敏な暗殺者集団だ。彼らはグルジンの率いるモンゴルの大軍勢と共にヒースムーアへ侵攻する。その目的は、グルジンが思い描く理想である、長きにわたり民たちを蝕んできた些末な戦乱から解放された平和なヒースムーアの実現。たとえ如何なる代償を払おうとも、グルジンの帝国の元に統一された平和なヒースムーアを作り上げるのだ。